| |
||||
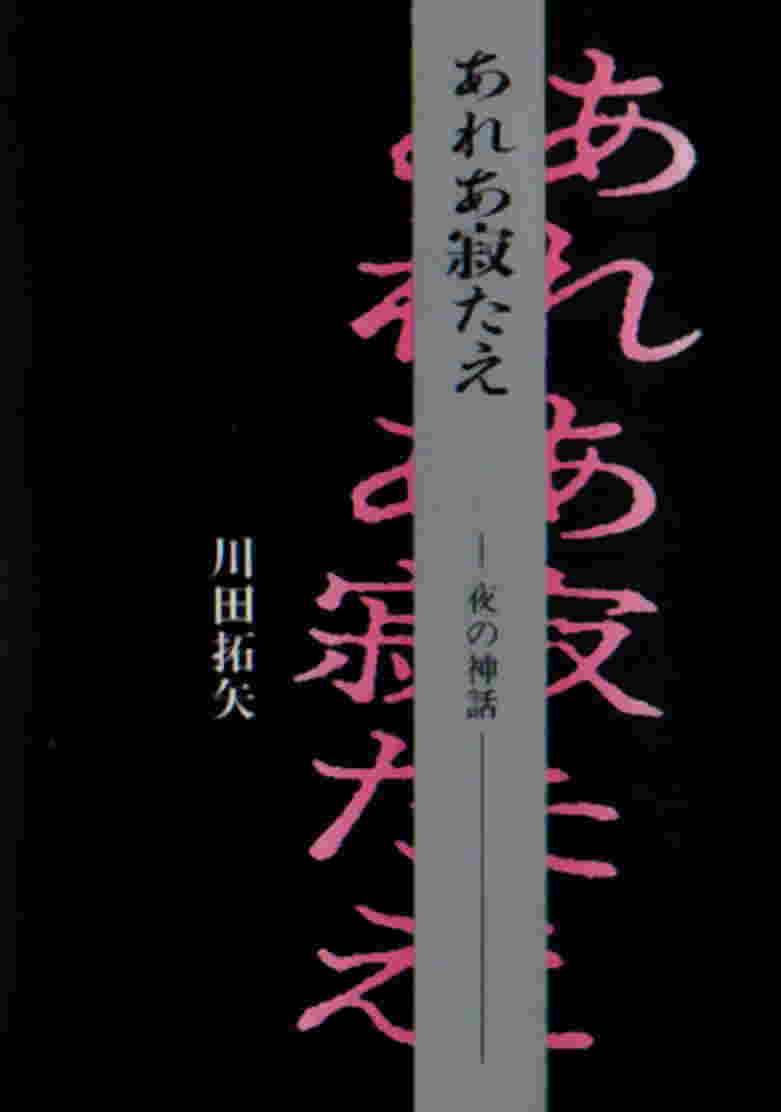 |
||||
| あれあ寂たえ夜の神話 著者:川田拓矢 出版社:近代文芸社 税込価格:2,415円 |
||||
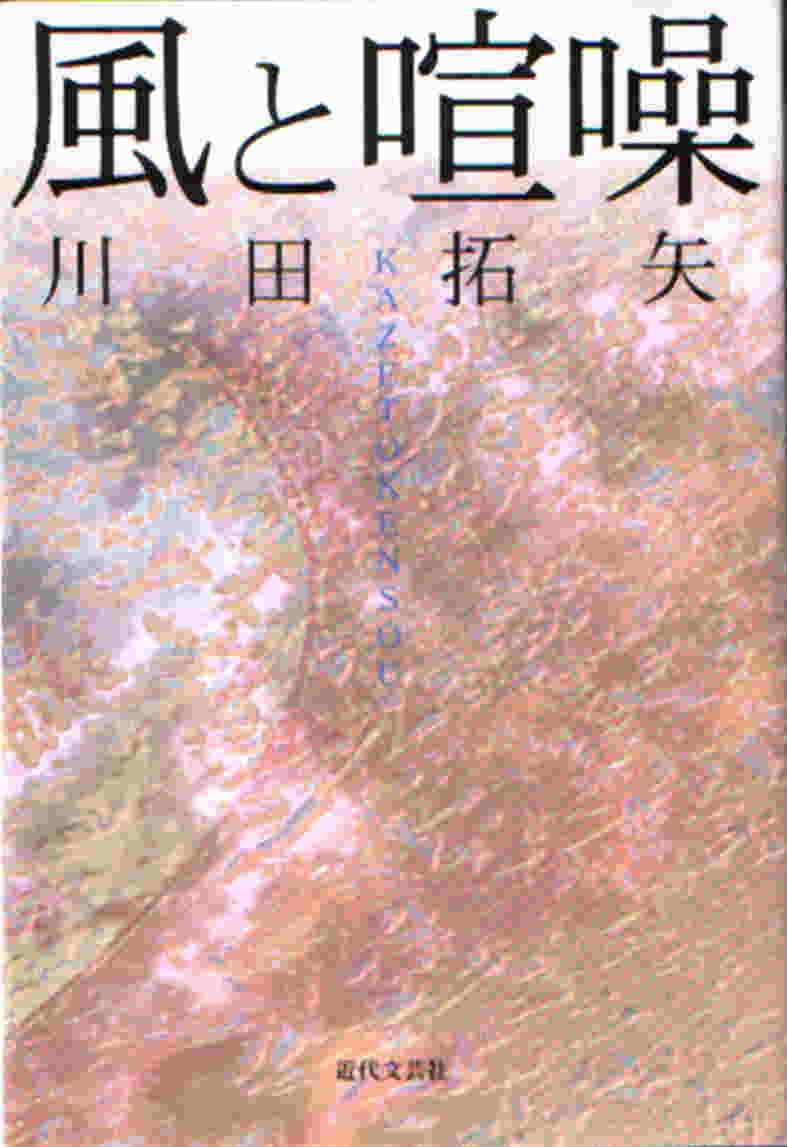 |
||||
| 風と喧噪 著者:川田拓矢 出版社:近代文芸社 本体価格:1,800円 楽天ブックスで購入する |
||||
心は熱く。瞳は涼やかに。 川田拓矢
遠い過去の人物を題材にして小説を書きたいと思っても、困るのは彼をめぐる女性の状況がはっきりわからないことだ。これは日本人が恋愛を露骨に著すことを卑しみ、かつ色欲に淡白であることを振舞おうとする民族だからにちがいない。私たちの歴史には個々の男は存在するけれども、個々の女というものは存在しない。それは往古よりつづいてきた系図に見られるとおり、永久に一人の〈女子〉であり、あるいは〈女〉なのである。
私の心中には、ほんとうによくよくの場合というものがない。どんなに困っても、いまだかつて痛切に、行き詰ったと感じた覚えはない。私はいつでも「どうにかなる」とたかをくくっている。そしてこの「どうにかなる」の一面には、「人間同士の義理さえ無視すれば」という条件が含まれている。 ところが、現実に私は人間同士の義理を一度も無視したことがない。それゆえ、いつも私は心の中ではなく生活の中でよくよくの場合に苦しみ、行き詰ったと感じ、どうにもならずに暮らしてきた。 とりわけ男女の問題では、ひたすらやけっぱちに暴れ回った。女が私の意見を理解しなかったり、聞き入れなかったりすると、つまり、人間同士の義理を軽視したような態度をすると、打ったり蹴ったりして半死半生の目に会わせた。そのままキチガイになるならなれというような捨て鉢な料簡で暴れ回るので、人間の義理のことで爆発したのにもかかわらず、頭の中には何もかも嵐で吹き飛ばされたように、人間らしい感情は少しも残っていなかった。その結果私には、かならずよくよくの場合がもたらされ、女はぷいと姿をくらまし、一日も二日も家を空け、どうかするとそのまま永遠に戻ってこないこともあった。 私は何がまちがっていたのかわからず、独りポツンと部屋の中に取り残されたまま、泣いたり笑ったりする元気もなく、なまくらになった頭を抱えながら、気を失ったように身を横たえて、うつらうつらと時の過ぎていくのを感じているばかりだった。
最近は、書きたがる徒輩がやたらに増えたようだ。時代の舞台を捜し求めて、われもわれもと書く。小説どころか、身のほども知らず詩まで書いているらしい。男も女も、老いも若きも、とにかく人生歴の一環として、一度でもスポットライトを浴びんがために書かなければ損というわけらしい。とはいえ、書かれるのは荒唐無稽な「怪異」か、素っ頓狂な「神話」か、迫真性のない「現実や事実」で、流行の舞台に載らない「愛」や「友情」という本物のテーマは書かれたためしがない。くだらないものとして疎まれているからだ。 激したり論じたりしていたころは(それは十五六歳から三十代半ばまでつづいた)、文化の動向がそんなふうに無機的に曲がっていった責任の一端が、たとえ微小でも自分のような有機的な芸術を志向する人間の怠惰と寡黙にあると思っていた。それは見当外れだった。誠実な人間の側に何の落ち度もなかった。 世の中にはいわゆる「飲み友達」というものがあって、酒を飲むときのほかにはとんと交渉がないというような間柄がたびたびある。酒の上ではずいぶん親しい仲ではあるけれども、結局その場かぎりの付き合いというやつである。自分の長い経験から考えて、たいがいの集いの場での人間関係も、それと似たり寄ったりであると思われる。彼らにはいい加減な応対をすればいいという特権がだれにでも許されている。なるほど賃取り仕事の場ではそんなふうだというのは首肯できるが、近ごろの世情を瞥見したり仄聞したりするところによれば、利害がほとんど関わってこない学校でも、クラブ活動でも、いや家庭内でさえそんなふうだと忖度されるのである。 つくづく私は人なつっこいよき時代に暮らしてきたものだと思う。家庭でも(飯場ではあったが)、学校でも、長じては大学でも飲み屋でも、さらに長じては職場でも、思わぬ行き掛かりから友情や親交を深めることができた。しかもそれが永続的なものであった。その幸運がいまもって私に、愛と友情の《嘘物語》を書かせつづける所以である。
|
|||||||||