祝 週言一周年おめでとう。
私は人に去られる悲しさを知っている。だから決して人から去らない。逆に人が私から去った場合、悲しみを自分だけのダイアとして純化させる。むろん、純化の度合いを高めるために、去った者を追うことは金輪際しない。 かつて私は、よく人を追いかけたものだった。追えば何かの回復がなるかと思って。虚しい営為だった。追うことでますます、去ろうとする者を苦しめた。去る者にとって、別れは美しいドラマであり、再生と飛躍のバネであり、多くの新鮮な愛を求める道標であることを知った。彼らは去りたくて去るのであり、去りたくないのにやむを得ず去るのではないということも知った。 私には、「去る者日々に疎し」という悪達観はないし、「時がすべてを解決する」という投げやりな諦念もない。別れにドラマはないと思っている。それは破壊に過ぎないと思っている。破壊に美を感じることはできない。出会った以上、人は生涯、人生の道行きを共にすべきだと心から信じている。共生からもたらされる熟した愛情がなければ、複雑な人格と才能を備えた人間というものをどうやって理解することができるだろう。学問も、芸術も、人間も、長い共生と、それに伴う理解という喜びがなければ、全力で愛することなどできないのだ。
自転車に乗りながら朝の曇り空を見上げ、誇りという自己愛から解放された。私でないものになろうとして、生きる形を求めすぎてきたことに気づいた。手にコンビニで買った競馬新聞があり、校庭に小学生の声がしていた。これでいい。私はこう生きるしかなかった。目の底が熱くなり、すがすがしい涙が流れた。
正直でありたいなら、無能でいるのが最上の方法だ。無能な人は周囲の人びとに安心感を与えるので、正直な発言をしても無事でいられる。
正月明けに、八歳年下のTさんから、CDプレーヤーつきで真空管アンプをいただいた。柔らかくて、つやの利いた、それでいてカチンと芯のある音を出す。わが家のCDソフトのほとんどをその装置で聴き終えた。音がよいというだけで、生きているうれしさが体中に沁みわたる。JBLとジェフローランドとの組み合わせとはまた別種の、えもいわれぬ澄んだ音色である。Tさんの優しさがしみじみと胸にきた。 彼とは予備校に勤めはじめたころ、盛岡や秋田の出張授業で親しくなった。慶應出のくせに、早稲田をこよなく愛していた。 やがてTさんは私の文筆活動を聞きつけ、その生原稿を読み、陰に日に励ましつづけるようになった。ある雑誌の新人賞候補にのぼったのをきっかけに、ひとつふたつと私の作品が発表されていくようになると、そのつど最大限の賛辞を贈り、 「涙が止まりませんでした。素晴らしいものです。世が世ならノーベル賞も夢ではありません。しかし、川田さんの作品群は死後に光を放つでしょう」 と真顔で評した。私にだけでなく、人にもそう喧伝した。ある夜二人で酒を飲んだ帰り道、 「生涯にわたって友人でいてくれますか」 と尋くと、足を止め、私の顔を宵闇に確認しながら、 「はい」 と短く、真剣な声色で答えた。 以来、折につけ、彼からどれほど精神的な恩恵を被ってきたか計り知れない。世情に疎い私に流行の小説の種を提供し(そのすべてを私は等閑に付した)、長い鬱に落ちたときには、「川田さんの本質は明るさです。沈んでいるのは川田さんらしくありません」と手紙をよこし、タイムリーに表に誘い出して励ましてくれた。 彼の人情の厚さと、秘密のなさと、若い好奇心に基づいた精神的な深みが、私にいつまでも感激を失わせない。 出会ったころ、私はTさんと偶々それぞれが持っていた型ちがいのモンブランの万年筆を交換した。彼に手紙や賀状を書くときは必ずその万年筆で書く。すると彼は、顔を合わせる機会があったりすると、 「あれで書きましたね」 とうれしそうに言う。わかりましたか、と私もうれしそうに答える。何がそこから発展するというのでもない。ひたすらうれしいのである。 いま彼の要望で『五百野』を英訳している。一週間の一日をそれに充てる。もう二年にもなる苦しい仕事である。 「英訳さえしておけば、ノーベル賞も可能ですからね」 先日、私の親友Gと三人で寿司をつまんだとき、Tさんはそう言った。Gは一瞬驚いてTさんの顔をまじまじと見つめたが、揺るがない表情に感嘆して、 「いい考えだ。あんたはいいことを川田にしてくれた」 と言った。 Tさんがどういう方途でその作品を世に出してくれるのかわからないし、あるいはそれは互いの希望の果ての徒労に終わるのかもしれないが、とにかく私は彼の友情に殉じてこれから何年かをこのつらい仕事に捧げるつもりだ。もちろん彼がノーベル賞のことなど念頭にないことは重々承知している。彼一流の私に対する友情の表現なのだ。とにかく彼は私という人間が、いや私の作品が好きなのである。人は好かれたら、その愛に死にもの狂いで応えなければならない。愛を提供する人間のどんな思い込みにも、喜んで身を殉じなければならない。
|
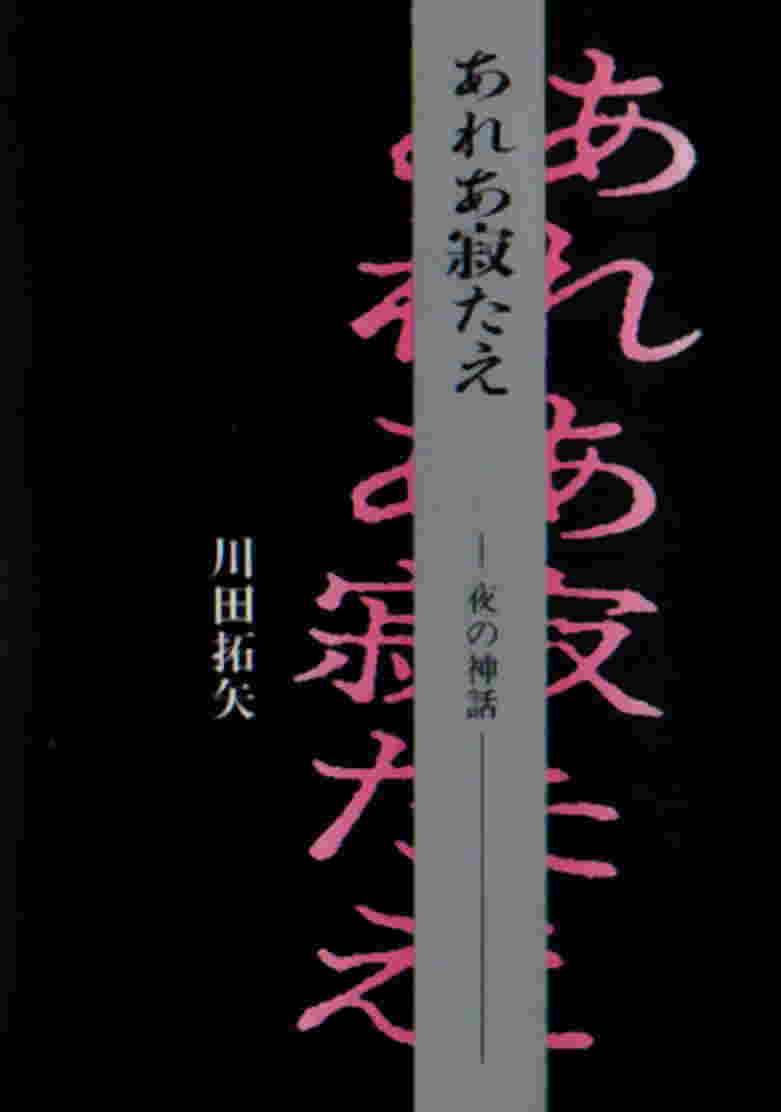 |
| あれあ寂たえ夜の神話 |
| 著者:川田拓矢 |
| 出版社:近代文芸社 |
| 本体価格:2,300円 |
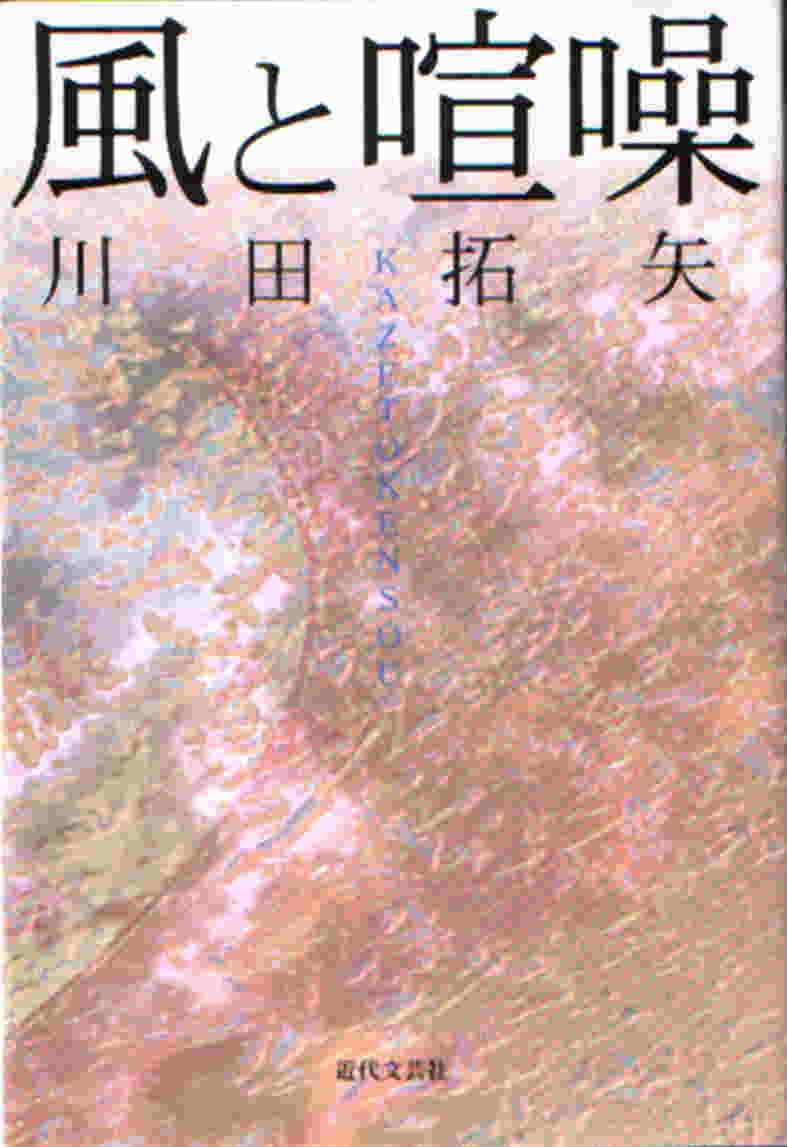 |
| 風と喧噪 著者:川田拓矢 出版社:近代文芸社 本体価格:1,800円 |
 |
| 光輝あまねき |
| 著者:川田拓矢 |
| 出版社:近代文芸社 |
| 本体価格:2,000円 |
| 「陸奥湾の潮騒がしみついた作家・川田拓矢」 ― 破綻にない緻密な文章。嫌味のない抑制のきいた表現と描写で崇高となっている ― ペンクラブ監事・「北狄」編集長笹田隆志 |